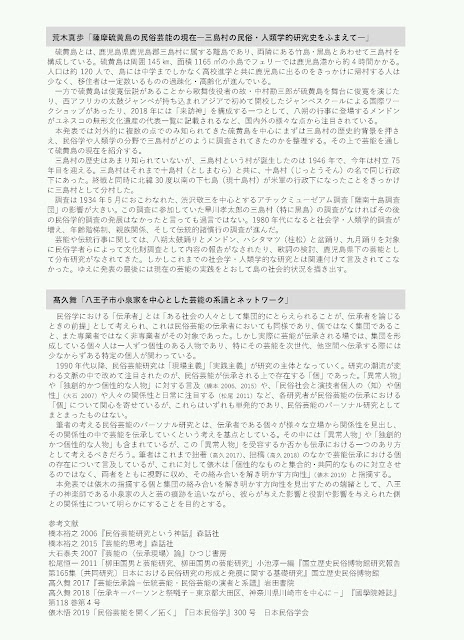第16回研究会を下記の通り開催いたします。
新型コロナウイルス感染拡大を鑑みオンライン形式で開催します。
多くのご参加をお待ちしております。
日時: 2021年3月20日(土)14:00~ (オンライン形式)
報告1: 荒木真歩 ( 神戸大学大学院 )
薩摩硫黄島の民俗芸能の現在ー三島村の民俗・人類学的研究史をふまえてー
硫黄島とは、鹿児島県鹿児島郡三島村に属する離島であり、
一方で硫黄島は俊寛伝説があることから歌舞伎役者の故・
本発表では対外的に複数の点でのみ知られてきた硫黄島を中心にま
三島村の歴史はあまり知られていないが、
調査は1934年5月におこわなれた、
芸能や伝統行事に関しては、八朔太鼓踊りとメンドン、
三島村の歴史はあまり知られていないが、
調査は1934年5月におこわなれた、
芸能や伝統行事に関しては、八朔太鼓踊りとメンドン、
報告2:髙久舞(國學院大學兼任講師)
八王子市小泉家を中心とした芸能の系譜とネットワーク
民俗学における「伝承者」とは「
1990年代以降、民俗芸能研究は「現場主義」「実践主義」
筆者の考える民俗芸能のパーソナル研究とは、
本発表では俵木の指摘する個と集団の絡み合いを解き明かす方向性
参考文献
橋本裕之2006『民俗芸能研究という神話』森話社
橋本裕之2015『芸能的思考』森話社
大石泰夫2007『芸能の〈伝承現場〉論』ひつじ書房
松尾恒一2011「柳田国男と芸能研究、柳田国男の芸能研究」
高久舞2017『芸能伝承論-伝統芸能・民俗芸能の演者と系譜』
高久舞2018「伝承キーパーソンと祭囃子-東京都大田区、
1990年代以降、民俗芸能研究は「現場主義」「実践主義」
筆者の考える民俗芸能のパーソナル研究とは、
本発表では俵木の指摘する個と集団の絡み合いを解き明かす方向性
参考文献
橋本裕之2006『民俗芸能研究という神話』森話社
橋本裕之2015『芸能的思考』森話社
大石泰夫2007『芸能の〈伝承現場〉論』ひつじ書房
松尾恒一2011「柳田国男と芸能研究、柳田国男の芸能研究」
高久舞2017『芸能伝承論-伝統芸能・民俗芸能の演者と系譜』
高久舞2018「伝承キーパーソンと祭囃子-東京都大田区、
俵木悟2019「民俗芸能を開く/拓く」『日本民俗学』300号 日本民俗学会
※参加される方はお申込みフォームよりお申し込みください(3月19日締め切り)。
※Zoomを使用します。