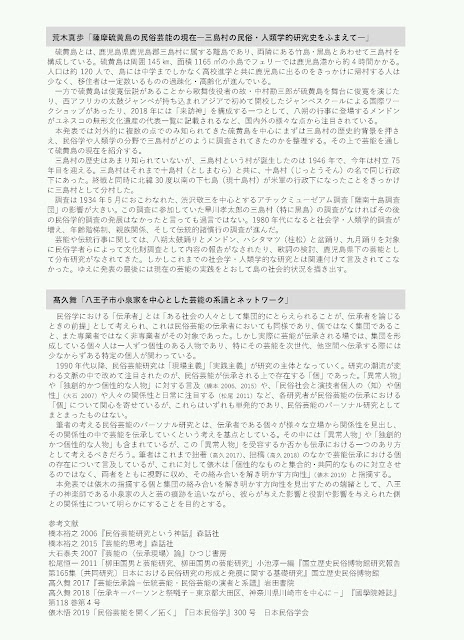第17回研究会を下記の通り開催いたします。
ふるってご参加ください。
日時: 2021年6月19日(土)14:00~ (オンライン形式)
※参加される方はお申込みフォームよりお申し込みください(6月16日締め切り)。
※Zoomを使用します。対応するブラウザはChrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Apple Safariです。当日、ミーティング情報をお申込み時にいただいたメールアドレスにお送りします。
報告1:伊藤純(川村学園女子大学)
「「伝承者」と言われて・・・―芸能研究におけるオートエスノグラフィ分析」
発表者は毎年8⽉に故郷の神社のお祭りで獅⼦舞を奉納し続けている。かれこれ20年になるかと思う。そのためか、しばしば「獅⼦舞の伝承者」として紹介されることがある。こうした「伝承者」というラベルを貼られるたびに、その状況を受け⼊れながらも、「伝承者」という⾔葉に違和感を覚え、時には地元の仲間に対する後ろめたさを感じていた。発表者がすすんで「伝承者」と名乗ることはほとんどない。
俵⽊悟は「「伝承者」とか「担い⼿」というような⾔葉を、ある⺠俗芸能を担う複数の、様々な⽴場の⼈々を⼗把⼀からげにして、違和感を感じることもなく使い続けてきたという点で、⺠俗芸能研究の右に出るものはないのではないか。」とこの⾔葉に疑問を呈している[俵⽊2009]。その指摘より10余年経った現在もさして状況は変わらない。むしろ、東⽇本⼤震災やコロナ禍としばしばセットで取り上げられる「⺠俗芸能の危機」とあいまって「伝承者」という⾔葉の存在がますます⼤きくなっている。
そこで本発表では⺠俗芸能に関わる⼈々を「伝承者」と⾔い表すことによって「顕在化されるもの/潜在化されるもの」について考察する。そのために「伝承者」と⾔われ続けて久しい発表者じしんのこれまでの経験を社会的⽂脈に置き直し、分析する。こうした⽅法はオートエスノグラフィという⽅法にあたるが、本発表では「調査者が⾃分⾃⾝を研究対象とし、⾃分の主観的な経験を表現しながら、それを⾃⼰再帰的に考察する⼿法」として捉えておく[井本2013]。実演者が少なくない芸能研究において、⾃⼰の経験を考察の対象とすることの意義も同時に⽰したい。
※参考文献
井本由紀2013「オートエスノグラフィー」『現代エスノグラフィー―新しいフィールドワークの理論と実践』新曜社
俵木悟2009「民俗芸能の「現在」から何を学ぶか」『現代民俗学研究』1
報告2:鈴木昂太(東京文化財研究所 研究補佐員)
「 芸態研究の可能性―岩手県北上市和賀大乗神楽の事例に基づいて―」
芸能文化研究会第14回研究会では、久保田裕道氏が「芸態研究のススメ」と題した発表をされた。芸態の分析方法をさまざまな実例を挙げて説明された久保田氏の問題提起は、今後の民俗芸能研究の在り方を考えるうえでも重要なものである。そこで今回の発表では、筆者なりの芸態研究の方法(可能性)を提示することを目的としたい。
芸態研究においては、「芸態」という言葉の定義を確認するとともに、以下の二つの問題が考えられる必要がある。
一つ目は、演ぜられている芸能を、どのように把握(理解)し、芸態として取り出すかという認識論的な課題である。一つの芸能は、舞(身体表現)や奏楽などさまざまな要素から成り立っている。そのうちの何を、どの視点から把握すれば、芸能を理解したことになるのだろうか。
二つ目は、把握した芸態(データ)を、どの視点から分析し、論として広げていくかという問題である。筆者は、ある一つの芸能の芸態を理解した後には、他の芸能との比較や論者それぞれの観点から考察を行うなどして、より多くの研究者の関心を集めるかたちで芸態(データ)を提示しなければならないと考えている。こうした「翻訳」の作業は、芸態研究を実りあるものとするためには必須である。ただの芸態分析に留まらず、芸態のあり方から立ち上げた論を広げる分析方法には、どのような視点があるのだろうか。
以上の課題を、岩手県北上市煤孫地区に伝承される和賀大乗神楽の事例に基づいて検討していきたい。その際には、神楽の伝承者が自身の舞を説明する際に語る「手次」という概念に注目して論じていく。